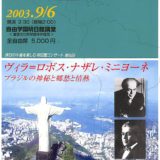プログラム ノート
ピアノ作品について
エイトル・ヴィラ=ロボス(1887-1959)は、彼自身ピアノを得意とし、前妻ルシリアもピアニストであったこともあり、ピアノの作品は特に数が多く質も高い。内容別に大まかに分類すると、①ブラジルのわらべ歌をヒントにした<民族的要素の濃いもの>、②音楽教育にも熱心に携わったため<子供を対象としたもの>、③<ヨーロッパ音楽からの影響と民族的なものとを融合させたもの>となる。
ブラジル風バッハ第4番より第1楽章
《前奏曲》(1941)
ヴィラ=ロボスが特に尊敬したバッハの精神と、ブラジルの民族的要素とを融合させた連作《ブラジル風バッハ》は、第1番から第9番まで大小さまざまな楽器編成で書かれている。《第4番》は9曲中唯一のピアノ独奏曲で、4楽章からなる。ロ短調のゆったりとしたテンポの第1楽章<前奏曲/序奏>は、郷愁と祈りを思わせる非常にロマンティックな作品で、本日同様に単独で演奏されることも多い。
野性の詩 (1921-26)
形容詞“rude”(粗野な)と名詞“poema”(詩)を結びつけた“合成語”をタイトルとするこの曲は、若き日のヴィラ=ロボスの自画像のようである。フランスへ渡った1923年をはさんで作曲されたためか、ドビュッシーやミヨーを思い出させる印象主義的な響きが聴こえたかと思えば、不協和音をともなった荒々しいリズムの中からブラジルのわらべ歌《Terezinha de Jesus(信心深いテレーサちゃん)》に似た旋律が断片的に聴こえてくる。テンポ、拍子、強弱の変化によって、雰囲気は次々と変化する。彼のピアノ作品中最も規模が大きく、独創的な力作である。
セレナード歌いの印象 (1936)
ブラジルの民族的な要素が濃い《Ciclo Brasileiro(ブラジル風連作)》全4曲中の第2曲目。“セレステイラス”とは夜のリオの町に流れる“セレスタ(セレナーデ)の奏者の集団”のことで、彼がまだ若い頃、ギターを手にこれらに加わった思い出が込められていると言われる。感傷的でノスタルジックなワルツは、どこかショパン風でもある。
歌曲(独唱曲)の作品について
ヴィラ=ロボスの歌曲は宗教曲なども加えて細かく数え上げると200曲以上もある。他のジャンル以上に民族的なものとの結びつきが強い。メロディラインは歌い手に時には過酷ともいえる条件を与えていることもあるが、彼の人間性および音楽性が最も自然な形でほとばしりでていて親しみやすい、という点で人気が高い。
枯葉の歌 (1926)
この曲はタイトルや歌詞の内容とはうらはらに明るく、最初から最後までハバネラ風リズム(ブラジルでは“ルンドゥ”と呼ばれるリズム)で貫かれている。ピアノによる少し長めの前奏部分が、リオで生まれた即興音楽“ショーロ”のような雰囲気を作りだす。その軽快なリズムに乗って、ソプラノがのびやかに歌いあげる。1923年から43年までの約20年間に書かれた全14曲《セレスタス(セレナーデ集)》の第3曲目。
カンティレーナ(小唄) (1938)
楽譜の冒頭に「黒人奴隷小屋で生まれた詩──バイーア州の……黒人のモティーフ」と記されている。二拍目にゴングのように打ち鳴らされる低いドの音(ピアノ)が作り出す重苦しい雰囲気の中で、ド-ミ♭-ソ-シ♭-ドの音だけを使った旋律が静かにゆったりと歌われる。黒人霊歌に似た楽想をもつ“カンソン”である。7つの曲をまとめた歌曲集《モジーニャとカンソン第1集》の第3曲目で、“モジーニャ” とは18世紀頃に起こったブラジルの叙情歌曲、“カンソン”とは一般的な歌のことを指す。
サントス公爵夫人のルンドゥ (1941)
“ルンドゥ”は18世紀に起源を持つブラジルの古い踊りの歌で、軽快な曲調をもつ。“サントス公爵夫人”とはブラジルのドン・ペドロ1世の有名な愛人のことであり、内容が悲しい恋物語であるためか、リズムは“ルンドゥ”でありながらも、寂しげな“モジーニャ”調である。前曲と同じ《モジーニャとカンソン第1集》の第2曲目。
室内楽作品について
彼の特徴は、既存の形式に囚われず自らの音楽に対する感性を大切にしていることである。このため交響曲やオペラなどの大掛かりな作品には構成力を欠くという弱点もあるが、短くまとめ上げられた小編成の作品には質の高い作品が多い。他の作曲家には見られない自由な楽器編成や伝統にとらわれない独自の和声法などが、彼の室内楽の魅力である。
クラリネット、バスーン、ピアノのための
《ファンタズィア・コンセルタンテ》 (1953)
“ファンタズィア・コンセルタンテ”という題名は、“幻想交響曲”や “幻想即興曲”などの曲名にちなんで彼が考え出した“造語”であろう。彼は“幻想曲”の形式そのものよりも、「伝統的な形式にとらわれずに、作曲家の幻想の赴くまま作曲された楽曲」というアイデアを好み、他のいくつかの作品にもこの名前をつけている。この“協奏的”幻想曲は、2本の管楽器とピアノを独奏楽器に選び、各々の技を見事に競わせている。躍動感のある第1・第3楽章でのテーマの展開の仕方も見事で、叙情性豊かな第2楽章は最も彼らしい。死の6年前の66歳の時に作曲されただけあって、ブラジルらしさに頼ることもなく、文字通り円熟期の作品に仕上がっている。
《ブラジル風バッハ》について
このシリーズは1930年から45年までの15年間(43~58歳)に9曲完成された。1930年といえば、1923年以来のパリ遊学を終えて帰国した年である。ヨーロッパ滞在中は連作《ショーロ》のような民族色豊かな作品を多く書いた彼だが、帰国後は全世界に向けて自分にしか書けない音楽を表現しようと試みる。その願いと、偉大なバッハの普遍的な音楽性への憧れをタイトルに込めたとされる。各曲の楽章全てに“バッハ風”と“ブラジル風”の2つの副題がつけられていることや音楽的内容から考えて、“バッハ風そしてブラジル風の音楽”といったところであろうか。
ブラジル風バッハ第5番 (1938/45)
《第5番》はソプラノ独唱を8台のチェロで伴奏するという珍しい形をとる。第1楽章(1938)が“バッハ風”の アリアで、第2楽章(1945)が“ブラジル風”の歌である。甘く美しいメロディで特に名高い第1楽章<アリア>は、実のところ演奏者泣かせでもあるという。高音部での息の長いフレーズの発声法はもちろんのこと、何と言ってもポルトガル語の正確な発音と詩の抑揚が難しい。ゆっくりとした雰囲気が一転し、第2楽章は早口言葉のようでこれもまた難しい。人気抜群の歌曲である。
ブラジル風バッハ第1番 (1930/38)
この連作最初の曲として8部のチェロオーケストラのために書かれ、そのユニークな編成と“バッハ風”である以上に“ブラジルらしい”雰囲気ゆえに、彼の全作品中で最もよく知られている。第1楽章の副題“エンボラーダ”とはブラジルの軽快な民謡・民族舞曲の一種を指す。第2楽章のゆるやかで美しい旋律に対してつけられた副題は“モジーニャ”である。第3楽章の副題“コンヴェルサ”とは「対話」という意味で、ここでは“ショーロ”の音楽家4人が互いに音による対話を重ねながら、自然にフーガを織りなしている情景をあらわしている。
市村由布子
Yuko Ichimura